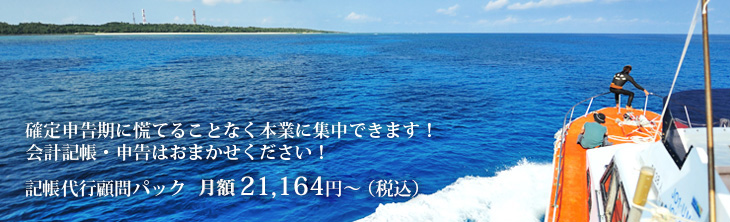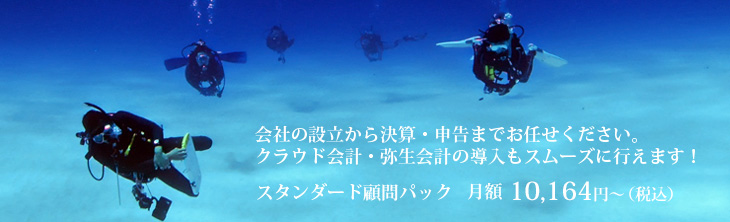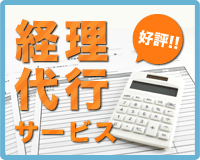年が明け事業者の方は前年分の会計をまとめておられる頃だと思いますが、2019年の会計をまとめていくにあたって、消費税の課税事業者が注意すべきは「消費税の税率区分」です。特に問題となるのは2019年10月以降の取引です。今回は、どのように区分するかを簡単にまとめてみました。
消費税の計算方法
[原則課税]
納付税額=売上に係る消費税額-仕入等に係る消費税額
*仕入等に係る消費税額は、課税売上割合が95%以上の場合全額控除できます。
[簡易課税]
納付税額=売上に係る消費税額-売上に係る消費税額×みなし仕入率
*1 みなし仕入れ率
・第1種事業 卸売業 90%
・第2種事業 小売業、農林水産業(食用) 80%
・第3種事業 鉱業、建設業、製造業 農林水産業(非食用) 70%
・第4種事業 飲食店業(1~3、5~6種事業以外の事業) 60%
・第5種事業 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く) 50%
・第6種事業 不動産業 40%
*2 簡易課税制度の適用を受ける場合は、原則は適用を受ける課税期間の前日までに届け出が必要です。
*3 基準期間の課税売上が5,000万円を超える場合は簡易課税制度を適用できません。
売上等
売上等を集計するにあたり、基本は9月30日までは8%、10月1日以降は10%(軽減税率8%事業者は軽減税率8%)となりますので、あとで消費税を計算できるように税率毎に区分して集計を行う。
特に、2019年10月分の売上請求書控は確認が必要です。末締めであれば10月分は、10/1~31までの売り上げとなりますが、例えば、20日締の場合の10月分は、9/21~10/20までの売り上げとなりますので、9/21~30までは8%、10/1~10/20までは10%と税率区分して会計をまとめる必要があります。
*原則課税・簡易課税共通して課税売上は必ず区分が必要です。
仕入等
仕入等を集計するにあたり、基本は9月30日までは8%、10月1日以降は10%(軽減税率8%)となりますので、あとで消費税を計算できるように税率毎に区分して集計を行う。
特に、2019年10月分の仕入等の請求書は確認が必要です。末締めであれば10月分は、10/1~31までの仕入等となりますが、例えば、20日締の場合の10月分は、9/21~10/20までの仕入等となりますので、9/21~30までは8%、10/1~10/20までは10%と税率区分して会計をまとめる必要があります。
自動振替の取引も注意が必要です。例えば、電話代の10月の自動振替は9月分であることが多く、9月分である場合は、10/1以降の振替であっても8%で集計する必要があります。
*原則課税のみ。簡易課税はみなし仕入率を使うため課税仕入等の集計は不要です。
2019年10月1日以後に適用する消費税等に関する経過措置
消費税の2019年10月以後の集計にあたり経過措置がありますので注意ください。
[経過措置項目]
・旅客運賃等
・電気料金等
・請負工事等
・資産の貸付け
・指定役務の提供
・予約販売に係る書籍等 など
*詳細は国税庁の2019年10月1日以後に適用する消費税等に関する経過措置リーフレットを確認ください。
このように2019年度の会計は消費税の区分を行います。ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、今年から消費税の申告が必要な方や消費税の計算がわからない事業者の方の確定申告をサポートしていますので、お気軽にご相談ください。